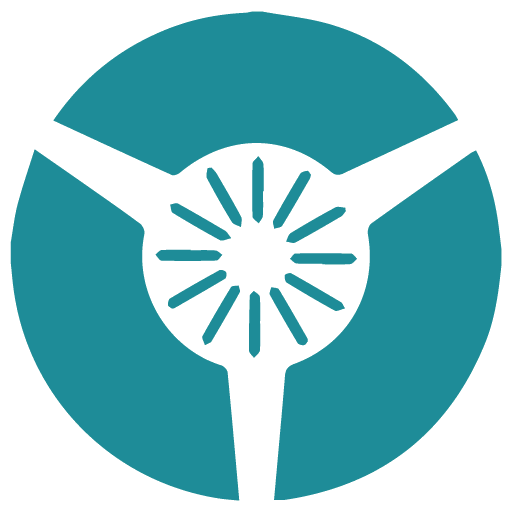8月19日、県農政部1名・役場農林課2名が、2回目の経過視察。
日差しが強く、日陰のない畑での視察、早く終わるかと思いきや、意外とゆっくり、じっくりの視察。
道上の実証圃場3655で、葉っぱにヨトウムシ(夜盗虫。蛾の幼虫)のちいさいのが、ところどころいたのを見た県農政部の人から、「葉っぱの中にもぐられる前の、薬剤散布にちょうどいい時期ですね」と言われた。
自分でも、時間をすこし作って散布しなければ、という気持ちがあったけれど、夏の植え替えの追い込み中だったこともあり、植え替え優先した。
4日後の、23日夕方、畑を通りがけにみたら、葉っぱを食いつくされていて、翌24日、慌てて薬剤散布(グレーシア乳剤20ℓ)。
小さい株は新芽まで食いつくされていて、食害痕から軟腐病の菌に感染し茶枯れた株は除去し、それ以外はまだ復活の可能性もあるので、そのままに。

害虫による食害と、雨が降らない高温乾燥が続いているためか、葱があっという間に悪くなった。
たとえば、7月17日、地温上昇を抑えるため、作間(条間)に大麦を蒔いたけれど(下画像)、その後、雨がほとんど降らないため、結局、大麦の芽が出ていない。それくらい雨がない。

同じ馬山地区でも、インターチェンジ付近では雷雨が数回あったが、ウチの畑のある道の駅周辺は、突風とゴロゴロ鳴るだけで雨が落ちない。日照りの夏。
8月26日、道下の実証圃場3352の草むしり。

雑草は主に(地元ではハグサと呼ばれる)メヒシバ。根の張りの弱い葱が多く、雑草と一緒に抜けてしまう。


ついでにヨトウムシも潰しながら、27日、むしり終わる。


翌28日は、道上の実証圃場3655の草むしり。

下画像は、7月14日、夏の植え替えをした直後の実証圃場3655。
その次の画像は、9月1日、同じ角度から。


7月中旬からほぼ降雨なし&ヨトウムシによる食害で、急激に悪くなった。
周りの岩山の木々も、紅葉と思いきや、降雨がないため、枯れ始めている。